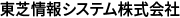進化するモビリティ社会に対応する、車載ソフトウェア開発センターを新設
自動車業界が電動化・自動運転・コネクテッドといった大きな転換期を迎える中、車載ソフトウェアはクルマの“頭脳”として、ますます重要な役割を担うようになります。
東芝情報システムでは、こうした技術革新と市場拡大の波に先手を打つべく、2025年1月、車載ソフトウェア開発センターを新設。分散していた開発体制を一つに集約し、開発効率と品質の両立を実現する新たな拠点が本格始動しました。
今回は、プロジェクトの中心メンバーである堀野さんに、車載ソフトウェア事業の全体像とともに、新開発センターの設立背景、設備、今後の展望について伺いました。
東芝情報システムでは、こうした技術革新と市場拡大の波に先手を打つべく、2025年1月、車載ソフトウェア開発センターを新設。分散していた開発体制を一つに集約し、開発効率と品質の両立を実現する新たな拠点が本格始動しました。
今回は、プロジェクトの中心メンバーである堀野さんに、車載ソフトウェア事業の全体像とともに、新開発センターの設立背景、設備、今後の展望について伺いました。


エンベデッドソリューション事業部
堀野 貴之
東芝情報システムの車載ソフトウェア事業

ひと口に車載ソフトウェアといっても、運転をサポートする先進運転支援システム(ADAS)、走行や安全を支える制御系など、さまざまなソフトウェアがクルマ全体を支えています。今回は東芝情報システムが担う車載ソフトウェア事業の全体像についてお話を伺いました。
ー車載ソフトウェア事業の主な領域を教えてください。
当社ではクルマを動かすためのソフトウェアを幅広く開発しています。その中で、車載ソフトウェア開発センターで担当しているのは、先進運転支援システムです。これは、人や障害物を検知してブレーキをかけたり、車線に沿って走行したりと、運転者を支援するためのシステムです。
中部支社(愛知県名古屋市)や関西支社(大阪府大阪市)などでは、エンジンやトランスミッションを制御するパワートレイン系、モーターやインバーターを制御するパワーエレクトロニクス系、メーターやヘッドアップディスプレイといったインパネ系、さらにはパワーウインドウやパワーステアリングなどのボディ系まで、さまざまな領域を手がけています。これらを総合すると、クルマに関わるほぼすべてのソフトウェア開発を担っていることになります。
ー車載ソフトウェアの重要性が高まる背景には、どのような業界の変化があるのでしょうか?
自動車業界は今、100年に一度と言われる大きな変革期を迎えています。運転支援技術や電気自動車向けのモーターなど、環境対応や安全性向上を目的とした技術開発がどんどん加速している状況です。
さらに最近注目されているのが「ソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)」という考え方です。これは“ソフトウェアがクルマそのものを定義する”というもので、従来のクルマづくりを大きく変えるものです。
これまでクルマの競争力を左右してきたのは、エンジンの性能やデザインでした。しかし今後は、ソフトウェアによってどのような機能を提供できるかが、大きな差別化のポイントになっていくと考えられます。
ー東芝情報システムとして、こうした変化をどのように捉えていますか?
ー車載ソフトウェア事業の主な領域を教えてください。
当社ではクルマを動かすためのソフトウェアを幅広く開発しています。その中で、車載ソフトウェア開発センターで担当しているのは、先進運転支援システムです。これは、人や障害物を検知してブレーキをかけたり、車線に沿って走行したりと、運転者を支援するためのシステムです。
中部支社(愛知県名古屋市)や関西支社(大阪府大阪市)などでは、エンジンやトランスミッションを制御するパワートレイン系、モーターやインバーターを制御するパワーエレクトロニクス系、メーターやヘッドアップディスプレイといったインパネ系、さらにはパワーウインドウやパワーステアリングなどのボディ系まで、さまざまな領域を手がけています。これらを総合すると、クルマに関わるほぼすべてのソフトウェア開発を担っていることになります。
ー車載ソフトウェアの重要性が高まる背景には、どのような業界の変化があるのでしょうか?
自動車業界は今、100年に一度と言われる大きな変革期を迎えています。運転支援技術や電気自動車向けのモーターなど、環境対応や安全性向上を目的とした技術開発がどんどん加速している状況です。
さらに最近注目されているのが「ソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)」という考え方です。これは“ソフトウェアがクルマそのものを定義する”というもので、従来のクルマづくりを大きく変えるものです。
これまでクルマの競争力を左右してきたのは、エンジンの性能やデザインでした。しかし今後は、ソフトウェアによってどのような機能を提供できるかが、大きな差別化のポイントになっていくと考えられます。
ー東芝情報システムとして、こうした変化をどのように捉えていますか?

ソフトウェアがクルマを形作るということは、それだけ車載ソフトウェアの規模や複雑さが増していくことを意味します。開発する側にとっては大変な面もありますが、一方でこれは新しい価値を生み出す大きなチャンスでもあると捉えています。
私たちはそのチャンスをしっかり受け止め、今後ますます複雑で大規模化するソフトウェアの需要に応えられるよう、技術力を高めていきたいと考えています。また高い品質を維持しながらスピーディーな開発を実現するための、体制や対応力の強化も必要だと考えています。
ー技術の進化が進む中で、車載ソフトウェアが社会のために果たしている役割についても教えていただけますか?
まずは、安全性の向上です。車載ソフトウェアによる運転支援では、前方の車両や歩行者を検知して、自動でブレーキをかける機能があります。またクルマの死角にいる車両や人も、センサーを活用して検知し、危険を察知することが可能です。こうしたシステムが安全性を高め、交通事故のリスクを大幅に減らしています。
次に、環境負荷の低減にも貢献しています。電動化の分野では、モーターなどの制御技術を高度化することでCO₂排出量の削減を実現できています。他にもさまざまな取り組みが進められていますが、安全性向上と環境負荷低減の2点が、特に大きな社会貢献だと考えています。
私たちはそのチャンスをしっかり受け止め、今後ますます複雑で大規模化するソフトウェアの需要に応えられるよう、技術力を高めていきたいと考えています。また高い品質を維持しながらスピーディーな開発を実現するための、体制や対応力の強化も必要だと考えています。
ー技術の進化が進む中で、車載ソフトウェアが社会のために果たしている役割についても教えていただけますか?
まずは、安全性の向上です。車載ソフトウェアによる運転支援では、前方の車両や歩行者を検知して、自動でブレーキをかける機能があります。またクルマの死角にいる車両や人も、センサーを活用して検知し、危険を察知することが可能です。こうしたシステムが安全性を高め、交通事故のリスクを大幅に減らしています。
次に、環境負荷の低減にも貢献しています。電動化の分野では、モーターなどの制御技術を高度化することでCO₂排出量の削減を実現できています。他にもさまざまな取り組みが進められていますが、安全性向上と環境負荷低減の2点が、特に大きな社会貢献だと考えています。
車載ソフトウェア開発の急拡大と新拠点設立の狙い

電動化や先進運転支援システムの普及により、車載ソフトウェアの開発量は今後5年間で約3倍に増えると予測されています。急速な市場変化に対応し、スピードと品質を両立するため、東芝情報システムは2025年1月に「車載ソフトウェア開発センター」を新設。その狙いを伺いました。
ー新たな開発拠点を設立された背景について、お聞かせいただけますか?
先ほどもお話ししたように、車載ソフトウェアの技術は急速に進歩しています。変化の激しい業界で競争力を維持するには、開発のスピードと品質の両立が不可欠であり、そのための体制づくりが非常に重要です。
そこで今回、川崎本社に隣接するビル内に車載ソフトウェア開発センターを新設しました。本センターは、専門的なスキルを持つメンバーがより密に連携できる環境を整え、効率的で迅速かつ高品質な開発を実現することを目的としています。
ー今後、車載ソフトウェアの開発量や求められる技術には、どのような変化が予想されますか?
一説によると、今後5年間で車載ソフトウェアの開発量は約3倍に増加すると予測されています。特に大きな成長が見込まれるのが電気自動車や、本センターで担当している先進運転支援システムです。
車載ソフトウェアはますます高度かつ複雑な機能が要求され、仕様やユーザーニーズの変化も今以上に激しくなるでしょう。こうした変化に柔軟かつ迅速に対応するため、開発体制の強化は欠かせません。
ー新たな開発拠点を設立された背景について、お聞かせいただけますか?
先ほどもお話ししたように、車載ソフトウェアの技術は急速に進歩しています。変化の激しい業界で競争力を維持するには、開発のスピードと品質の両立が不可欠であり、そのための体制づくりが非常に重要です。
そこで今回、川崎本社に隣接するビル内に車載ソフトウェア開発センターを新設しました。本センターは、専門的なスキルを持つメンバーがより密に連携できる環境を整え、効率的で迅速かつ高品質な開発を実現することを目的としています。
ー今後、車載ソフトウェアの開発量や求められる技術には、どのような変化が予想されますか?
一説によると、今後5年間で車載ソフトウェアの開発量は約3倍に増加すると予測されています。特に大きな成長が見込まれるのが電気自動車や、本センターで担当している先進運転支援システムです。
車載ソフトウェアはますます高度かつ複雑な機能が要求され、仕様やユーザーニーズの変化も今以上に激しくなるでしょう。こうした変化に柔軟かつ迅速に対応するため、開発体制の強化は欠かせません。
300人超の執務スペース&90席の実機検証環境を完備した最新鋭の設備

リフレッシュコーナーで談笑する若手メンバー
開発体制強化を支える新拠点には、広大な執務スペースと実機検証エリアを完備。快適さとセキュリティを両立した環境で、一層の開発力向上を目指しています。
ー新拠点の場所や規模、主な設備について教えてください。
約2600平米のワンフロアに、300名以上が働ける執務エリアと、90席以上の実機検証専用エリアを備えています。ソフトウェアの設計・開発から実機を使った動作検証まで、一貫して作業できる環境が整っています。
また打ち合わせスペースを広く設け、フリーアドレス席も20席ほど用意しているため、外部から来た人も作業ができるようになっています。さらにリフレッシュコーナーも設けており、多くの社員がリラックスしたりコミュニケーションを取ったりする場として活用しています。
このようにオープンなスペースが多い一方で、セキュリティ対策も徹底しています。共有エリアの奥には扉があり、セキュリティカードを持っていないと入れないようになっています。
開発体制強化を支える新拠点には、広大な執務スペースと実機検証エリアを完備。快適さとセキュリティを両立した環境で、一層の開発力向上を目指しています。
ー新拠点の場所や規模、主な設備について教えてください。
約2600平米のワンフロアに、300名以上が働ける執務エリアと、90席以上の実機検証専用エリアを備えています。ソフトウェアの設計・開発から実機を使った動作検証まで、一貫して作業できる環境が整っています。
また打ち合わせスペースを広く設け、フリーアドレス席も20席ほど用意しているため、外部から来た人も作業ができるようになっています。さらにリフレッシュコーナーも設けており、多くの社員がリラックスしたりコミュニケーションを取ったりする場として活用しています。
このようにオープンなスペースが多い一方で、セキュリティ対策も徹底しています。共有エリアの奥には扉があり、セキュリティカードを持っていないと入れないようになっています。
対面コミュニケーションで深まった連携が、開発効率を高める

打ち合わせスペースで談笑する若手メンバー
分散していた開発チームを一つに集約し、新たな体制がスタートしてから早半年。部門の垣根を越えた連携がどう変わったのか、その具体的な影響について伺います。
ー新拠点ではどのような開発体制が取られていますか?
一部で在宅勤務も取り入れていますが、できるだけ顔を合わせて仕事をすることを大切にしています。エンジニアやプロジェクトマネージャー、デザイナーなど、さまざまな部門のメンバーが集まることで部門間の垣根がなくなり、情報共有や意見交換が活発に行われています。その結果、開発チームに一体感が生まれ、効率的に高品質なものづくりが可能になりました。また意思決定や方針決定のスピードも格段に上がり、迅速な対応が実現しています。
ー対面でのコミュニケーションは、開発現場にどのような影響を与えたのでしょうか?
例えばインターフェースの仕様を決める際、以前は担当者同士で何度もメールをやり取りしていましたが、今では数十分の打ち合わせで決定できるようになりました。直接顔を合わせることで対話が深まり、意思決定が格段にスムーズになったと感じます。結果として、開発スピードの向上だけでなく、ソフトウェアの品質向上にもつながっています。
ーチーム間の連携や情報共有は、どうやって強化していったのですか?
対面でのコミュニケーションを重視したことで、自然と連携が深まりました。文字だけでは伝わりにくいニュアンスも、表情や反応を見ながら話すことでスムーズに共有でき、疑問点があればすぐに声をかけられます。
その結果、「目の前にいる相手を助けたい」という気持ちが高まり、担当外のことでも自然と手を差し伸べる風土が育っているように感じます。また若手メンバーからは、「職場にいつも笑い声や話し声が響いているから、雰囲気がよくて作業しやすい」という声が寄せられ、全体の士気向上にもつながっています。
分散していた開発チームを一つに集約し、新たな体制がスタートしてから早半年。部門の垣根を越えた連携がどう変わったのか、その具体的な影響について伺います。
ー新拠点ではどのような開発体制が取られていますか?
一部で在宅勤務も取り入れていますが、できるだけ顔を合わせて仕事をすることを大切にしています。エンジニアやプロジェクトマネージャー、デザイナーなど、さまざまな部門のメンバーが集まることで部門間の垣根がなくなり、情報共有や意見交換が活発に行われています。その結果、開発チームに一体感が生まれ、効率的に高品質なものづくりが可能になりました。また意思決定や方針決定のスピードも格段に上がり、迅速な対応が実現しています。
ー対面でのコミュニケーションは、開発現場にどのような影響を与えたのでしょうか?
例えばインターフェースの仕様を決める際、以前は担当者同士で何度もメールをやり取りしていましたが、今では数十分の打ち合わせで決定できるようになりました。直接顔を合わせることで対話が深まり、意思決定が格段にスムーズになったと感じます。結果として、開発スピードの向上だけでなく、ソフトウェアの品質向上にもつながっています。
ーチーム間の連携や情報共有は、どうやって強化していったのですか?
対面でのコミュニケーションを重視したことで、自然と連携が深まりました。文字だけでは伝わりにくいニュアンスも、表情や反応を見ながら話すことでスムーズに共有でき、疑問点があればすぐに声をかけられます。
その結果、「目の前にいる相手を助けたい」という気持ちが高まり、担当外のことでも自然と手を差し伸べる風土が育っているように感じます。また若手メンバーからは、「職場にいつも笑い声や話し声が響いているから、雰囲気がよくて作業しやすい」という声が寄せられ、全体の士気向上にもつながっています。
高度化する車載ソフトへの対応をどう進めていくのか

電動化や自動運転の進展により、車載ソフトウェアに求められる技術は日々高度化しています。最新技術のポイントや、若手の活躍についても伺いました。
ーどのような技術が求められていると思いますか?
特に自動運転では、さまざまなセンサーを使って周囲の情報を集め、物体を認識する技術が欠かせません。現在は、映像で物を認識するカメラ、そして距離を測るミリ波レーダーが主に使われていますが、加えてLiDARというセンサーで取得した点群データを用いて立体的に物を認識する技術も進んでいます。
例えば現在の自動駐車機能では、カメラが白線を認識し、そのラインに沿ってクルマを動かします。そのため、白線がない場合は自動駐車が難しくなってしまいます。一方、点群データは周囲の地形を詳細に認識できるため、白線のない場所でもより精度の高い自動駐車が可能となります。
これらの多様なセンサーからの情報を処理するには、高速かつリアルタイムの処理能力が求められます。さらに、ソフトウェアの不具合修正や機能追加のために、OTA(Over The Air)と呼ばれる無線でのソフトウェア更新技術も重要になっています。
ー若手の社員の活躍は可能なのでしょうか?
もちろん可能です。今活躍している社員も、かつては皆若手でした。ですから、若手の成長や活躍には大いに期待しています。むしろ、若手ならではの柔軟な発想やアイデアを積極的にぶつけてもらうことで、周りの社員への刺激にもなり、チームの活性化につながると考えています。
また、外部研修にも参加できる機会を設けており、社員一人ひとりのスキルアップや専門性の向上をしっかりサポートしています。
ーどのような技術が求められていると思いますか?
特に自動運転では、さまざまなセンサーを使って周囲の情報を集め、物体を認識する技術が欠かせません。現在は、映像で物を認識するカメラ、そして距離を測るミリ波レーダーが主に使われていますが、加えてLiDARというセンサーで取得した点群データを用いて立体的に物を認識する技術も進んでいます。
例えば現在の自動駐車機能では、カメラが白線を認識し、そのラインに沿ってクルマを動かします。そのため、白線がない場合は自動駐車が難しくなってしまいます。一方、点群データは周囲の地形を詳細に認識できるため、白線のない場所でもより精度の高い自動駐車が可能となります。
これらの多様なセンサーからの情報を処理するには、高速かつリアルタイムの処理能力が求められます。さらに、ソフトウェアの不具合修正や機能追加のために、OTA(Over The Air)と呼ばれる無線でのソフトウェア更新技術も重要になっています。
ー若手の社員の活躍は可能なのでしょうか?
もちろん可能です。今活躍している社員も、かつては皆若手でした。ですから、若手の成長や活躍には大いに期待しています。むしろ、若手ならではの柔軟な発想やアイデアを積極的にぶつけてもらうことで、周りの社員への刺激にもなり、チームの活性化につながると考えています。
また、外部研修にも参加できる機会を設けており、社員一人ひとりのスキルアップや専門性の向上をしっかりサポートしています。
業界の先陣を切る最強の開発組織を目指して

車載ソフトウェア開発センターが設立されて半年が経った今、今後どのように事業を展開し、組織を成長させ、社会に貢献していくのか、その展望を伺いました。
ー今後、本センターでどのように車載ソフトウェア事業を展開していきたいと考えていらっしゃいますか?
最新のソフトウェアをより高品質かつ安全に開発し、世に送り出せる環境を作りたいと考えています。また、そこでものづくりをする人たちが「これからもやり続けたい」と思えるような場所にしていきたいです。
車載ソフトウェアの開発は、品質や納期のプレッシャーが大きく、どうしても疲れてしまう時があります。でも、だからこそ皆で力を合わせて難局を乗り越え、「車載ソフトウェアって苦しい時も辛い時もあるけど、それでもやっぱりこのメンバーと次も一緒にやりたい」と思えるようなチームを作れたらと思います。
ー組織として、どのような方向を目指していきたいですか?
組織の方向性というのは、メンバー全員で決めていくものだと考えています。車載ソフトウェアの開発という大きな目標に対して、多様なアプローチがありますが、個々がバラバラな方向を向くのではなく、みんなで議論しながら最終的に一つのベクトルに向かっていける組織にしたいと思っています。時には意見が衝突することがあるかもしれませんが、それもコミュニケーションの一環として大切にしたいですね。
ー将来的に果たしたい社会的な役割があれば教えてください。
安全で、社会に貢献できる車載ソフトウェアの実現を目指しています。ただ単に既存技術の後を追うのではなく、先陣を切って道を拓く意気込みです。もちろん平坦な道のりではありませんが、そうした挑戦を重ねることで社会への貢献を果たせると信じています。
ー今後、本センターでどのように車載ソフトウェア事業を展開していきたいと考えていらっしゃいますか?
最新のソフトウェアをより高品質かつ安全に開発し、世に送り出せる環境を作りたいと考えています。また、そこでものづくりをする人たちが「これからもやり続けたい」と思えるような場所にしていきたいです。
車載ソフトウェアの開発は、品質や納期のプレッシャーが大きく、どうしても疲れてしまう時があります。でも、だからこそ皆で力を合わせて難局を乗り越え、「車載ソフトウェアって苦しい時も辛い時もあるけど、それでもやっぱりこのメンバーと次も一緒にやりたい」と思えるようなチームを作れたらと思います。
ー組織として、どのような方向を目指していきたいですか?
組織の方向性というのは、メンバー全員で決めていくものだと考えています。車載ソフトウェアの開発という大きな目標に対して、多様なアプローチがありますが、個々がバラバラな方向を向くのではなく、みんなで議論しながら最終的に一つのベクトルに向かっていける組織にしたいと思っています。時には意見が衝突することがあるかもしれませんが、それもコミュニケーションの一環として大切にしたいですね。
ー将来的に果たしたい社会的な役割があれば教えてください。
安全で、社会に貢献できる車載ソフトウェアの実現を目指しています。ただ単に既存技術の後を追うのではなく、先陣を切って道を拓く意気込みです。もちろん平坦な道のりではありませんが、そうした挑戦を重ねることで社会への貢献を果たせると信じています。
私たちと一緒に挑戦しませんか?

ー最後に、この記事を読んでいる学生の皆さんに向けて熱いメッセージをお願いします。
車載ソフトウェア開発は社会的意義が大きく、やりがいに満ちています。たしかに大変なこともありますが、その分楽しさや自己成長を実感できる環境でもあります。私が理想とする、メンバーからリーダーまでがフランクに会話ができる環境も、徐々に実現しつつあると感じています。お互いをリスペクトし合い、気持ちよく働ける環境ですので、ぜひ第一希望に選んでいただけたら嬉しいです。
毎年夏に開催している学生向けインターンシップや、産学連携のワークショップも、参加者の皆さんから毎回好評です。そちらも、ぜひお気軽にご参加ください!
※記事内における内容、組織名などは2025年9月公開時のものです。
※本文中の会社名および製品名は各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
車載ソフトウェア開発は社会的意義が大きく、やりがいに満ちています。たしかに大変なこともありますが、その分楽しさや自己成長を実感できる環境でもあります。私が理想とする、メンバーからリーダーまでがフランクに会話ができる環境も、徐々に実現しつつあると感じています。お互いをリスペクトし合い、気持ちよく働ける環境ですので、ぜひ第一希望に選んでいただけたら嬉しいです。
毎年夏に開催している学生向けインターンシップや、産学連携のワークショップも、参加者の皆さんから毎回好評です。そちらも、ぜひお気軽にご参加ください!
※記事内における内容、組織名などは2025年9月公開時のものです。
※本文中の会社名および製品名は各社が商標または登録商標として使用している場合があります。